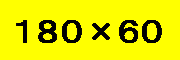【お知らせ】◆長野県産品を買いましょう! ◆長野県魅力発信ブログ
(
2008年08月28日発行)
|カテゴリー 木曽エリア|
いにしえから木曽は「木の国」として知られています。
大切に守られてきた木曽の森。
今も、ヒノキ、サワラ、ネズコ、アスナロ、コウヤマキからなる木曽五木が茂ります。とりわけヒノキは木曽ヒノキとしてなかには樹齢300年を超えるものも多く、非常に良い材として珍重されてきました。

左:楢川平沢地区の漆器 右:赤沢自然休養林
「木一つ、首一つ」という言葉をご存知でしょうか。
戦国から江戸時代。築城や街づくりの為に、木曽の木材は、乱伐が続きました。
良質の材木が藩力の礎と考えた徳川家康は、この林を自らの管轄に治めようとします。木曽は親藩の尾張徳川家の所有となり、尾張藩は地元農民による木曽五木の伐採を禁じたのです。
そのときのおふれが、「木一つ、首一つ」。
ヒノキ1本が、人の命と同じ…と、厳しく取り締まった歴史があります。
明治維新後も国有林として厳しく管理された木曽の森。厳しい取り締まりで命を落とした人もいたそうですが、そんな厳重な管理体制があったからこそ、江戸から現代まで、この木曽の美林が守られてきたと言うことができます。
■受け継がれる匠の手業
木曽で守られてきたのは良材だけではありません。良材を用いた「くりもの」「曲げ物」「漆芸」「櫛」「ろくろ細工」などの木工芸の技術もまた、木曽の森とともに職人の手から手へと受け継がれてきました。桶に杓子、わっぱ、椀、皿、櫛など日常使いの品が多くてかつ品質も高いことが、多くの人から愛され、そして今に至るまで長く続いてきた理由のひとつなのでしょう。
そのなかのひとつ、「くりもの」をご紹介しましょう。くりもの師は、木をノミでくりぬいて木工品を作ります。
ろくろを使って盆や椀を作る木地師(きぢし)とは違い、丸いものだけでなく、自在な造形が可能。伝統工芸として高く評価されながら、伝統工芸の域にはまらないクラフトともアートもいえる自由な作品を生み出しています。
 南木曽町の北原昭一さんは、今や数少ない「くりもの師」として活躍するひとり。
南木曽町の北原昭一さんは、今や数少ない「くりもの師」として活躍するひとり。
木地師の小椋榮一さんのもとで3年間ろくろを修業した後、自分の工房を構えてほぼ30年になるそうです。
主な素材は欅(けやき)、栃(とち)、栗(くり)、楓(かえで)、黒柿(くろかき)などの広葉樹の銘木。
ふさわしい形と大きさを決めることから始まり、細かい部分は削りながら決めていくそうです。「自分で考えているというよりは、木と向かい合っていると、自然が教えてくれる。自然が手伝ってくれる感じ」と北原さん(写真)は言います。
■「木曽の匠」に挑戦~ろくろ体験~
木曽の宿場沿いには多くの店や工房が軒を連ね、今でも木を削る音などが心地良く響きます。立ち並ぶ工房のなかには一般のお客が木工芸を体験できるところもあります。
今回は、代表的な「木曽の匠」を実際に体験してみましょう。
木地の美しさをそのままに生かすのが「ろくろ」。
その名も「ろくろ」と呼ばれる道具に木材を取りつけ、ノミをあてて丸くくりぬき、皿や盆、椀などを作るものです。
その始まりは平安時代。木地師と呼ばれる職人は、ろくろを背負って諸国の山々を歩いては製品を作ったのだとか。
かつては人力で紐を引きろくろを回したそうですが、今では電動が一般的で、体験施設などでは素人の私たちでも安全に作れるようになっています。

体験してみよう!
【1】まずは中心部にのみをあて、外側へ向って削ってゆきます。ノミの刃を当てる角度にコツがあり。
【2】20分ほどで、ろくろは終了。ささくれたり、深く削れすぎたりした部分はヤスリで滑らかにしましょう。
【3】仕上げに、電熱の焼ゴテを当てて、絵付けをします。お絵描きをするように楽しめますよ。
ほかにも奈良井の「曲物(まげもの)」や、「木曽漆器」の名で知られる漆器の漆塗り、華麗な「沈金」(漆にノミで下絵を彫り金箔や金粉などを入れ込み図柄を表現する)などの体験を行っている工房もあります。
好みの体験を選んで、旅の土産にいかがでしょうか。
木曽檜についてはこちら
南木曽の伝統工芸品やろくろ体験についてはこちら
木曽漆器についてはこちら(木曽漆器工業協同組合)
漆器体験についてはこちら
大切に守られてきた木曽の森。
今も、ヒノキ、サワラ、ネズコ、アスナロ、コウヤマキからなる木曽五木が茂ります。とりわけヒノキは木曽ヒノキとしてなかには樹齢300年を超えるものも多く、非常に良い材として珍重されてきました。

左:楢川平沢地区の漆器 右:赤沢自然休養林
「木一つ、首一つ」という言葉をご存知でしょうか。
戦国から江戸時代。築城や街づくりの為に、木曽の木材は、乱伐が続きました。
良質の材木が藩力の礎と考えた徳川家康は、この林を自らの管轄に治めようとします。木曽は親藩の尾張徳川家の所有となり、尾張藩は地元農民による木曽五木の伐採を禁じたのです。
そのときのおふれが、「木一つ、首一つ」。
ヒノキ1本が、人の命と同じ…と、厳しく取り締まった歴史があります。
明治維新後も国有林として厳しく管理された木曽の森。厳しい取り締まりで命を落とした人もいたそうですが、そんな厳重な管理体制があったからこそ、江戸から現代まで、この木曽の美林が守られてきたと言うことができます。
■受け継がれる匠の手業
木曽で守られてきたのは良材だけではありません。良材を用いた「くりもの」「曲げ物」「漆芸」「櫛」「ろくろ細工」などの木工芸の技術もまた、木曽の森とともに職人の手から手へと受け継がれてきました。桶に杓子、わっぱ、椀、皿、櫛など日常使いの品が多くてかつ品質も高いことが、多くの人から愛され、そして今に至るまで長く続いてきた理由のひとつなのでしょう。
そのなかのひとつ、「くりもの」をご紹介しましょう。くりもの師は、木をノミでくりぬいて木工品を作ります。
ろくろを使って盆や椀を作る木地師(きぢし)とは違い、丸いものだけでなく、自在な造形が可能。伝統工芸として高く評価されながら、伝統工芸の域にはまらないクラフトともアートもいえる自由な作品を生み出しています。

木地師の小椋榮一さんのもとで3年間ろくろを修業した後、自分の工房を構えてほぼ30年になるそうです。
主な素材は欅(けやき)、栃(とち)、栗(くり)、楓(かえで)、黒柿(くろかき)などの広葉樹の銘木。
ふさわしい形と大きさを決めることから始まり、細かい部分は削りながら決めていくそうです。「自分で考えているというよりは、木と向かい合っていると、自然が教えてくれる。自然が手伝ってくれる感じ」と北原さん(写真)は言います。
■「木曽の匠」に挑戦~ろくろ体験~
木曽の宿場沿いには多くの店や工房が軒を連ね、今でも木を削る音などが心地良く響きます。立ち並ぶ工房のなかには一般のお客が木工芸を体験できるところもあります。
今回は、代表的な「木曽の匠」を実際に体験してみましょう。
木地の美しさをそのままに生かすのが「ろくろ」。
その名も「ろくろ」と呼ばれる道具に木材を取りつけ、ノミをあてて丸くくりぬき、皿や盆、椀などを作るものです。
その始まりは平安時代。木地師と呼ばれる職人は、ろくろを背負って諸国の山々を歩いては製品を作ったのだとか。
かつては人力で紐を引きろくろを回したそうですが、今では電動が一般的で、体験施設などでは素人の私たちでも安全に作れるようになっています。

体験してみよう!
【1】まずは中心部にのみをあて、外側へ向って削ってゆきます。ノミの刃を当てる角度にコツがあり。
【2】20分ほどで、ろくろは終了。ささくれたり、深く削れすぎたりした部分はヤスリで滑らかにしましょう。
【3】仕上げに、電熱の焼ゴテを当てて、絵付けをします。お絵描きをするように楽しめますよ。
ほかにも奈良井の「曲物(まげもの)」や、「木曽漆器」の名で知られる漆器の漆塗り、華麗な「沈金」(漆にノミで下絵を彫り金箔や金粉などを入れ込み図柄を表現する)などの体験を行っている工房もあります。
好みの体験を選んで、旅の土産にいかがでしょうか。
木曽檜についてはこちら
南木曽の伝統工芸品やろくろ体験についてはこちら
木曽漆器についてはこちら(木曽漆器工業協同組合)
漆器体験についてはこちら
Vol.54■~木曽路はすべて山の中~ 木曽十一宿を巡る
Vol.53■山間の渓谷へ
Vol.51■赤沢自然休養林で森林セラピーを体験!
Vol.5特集■霊験あらたか、御嶽(おんたけ)山麓避暑の旅
Vol.4 特集■是より木曽路、中山道を往く旅
Vol.53■山間の渓谷へ
Vol.51■赤沢自然休養林で森林セラピーを体験!
Vol.5特集■霊験あらたか、御嶽(おんたけ)山麓避暑の旅
Vol.4 特集■是より木曽路、中山道を往く旅
|カテゴリー 木曽エリア|
カテゴリ
●週刊信州とは? (1)
└
サイトマップ (1)
■エリアで捜す (1)
└
佐久エリア (6)
└
上田エリア (7)
└
諏訪エリア (4)
└
上伊那エリア (6)
└
南信州エリア (6)
└
木曽エリア (6)
└
松本安曇野エリア (7)
└
北アルプスエリア (8)
└
長野エリア (7)
└
北信州エリア (6)
└
コラム (34)
■読まなきゃチョーソン市町村 (42)
■とく☆とく信州 (41)
■注目イベント (82)
■県からのお知らせ (94)
■なるほどNAGANO (75)
■動画で楽しむ信州の一週間 (83)
■旬の信州情報 (43)
■読者プレゼント (57)
■投稿写真 (5)
■はみ出し情報 (3)
□配信登録と停止 (2)
□個人情報の取扱い (14)
□動画をご覧いただくために (1)
□広告につきまして (0)
過去記事
「週刊信州」内の検索はこちら
発行

長野県庁企画部企画課
QRコード
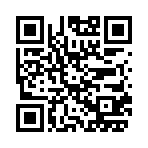
インフォメーション